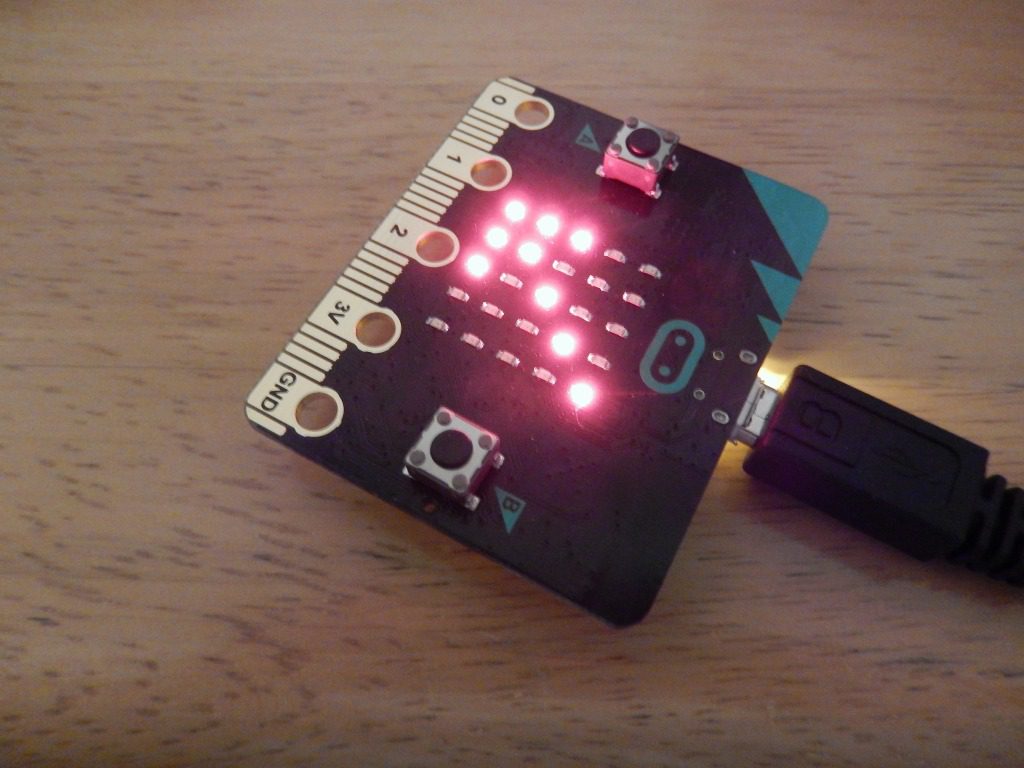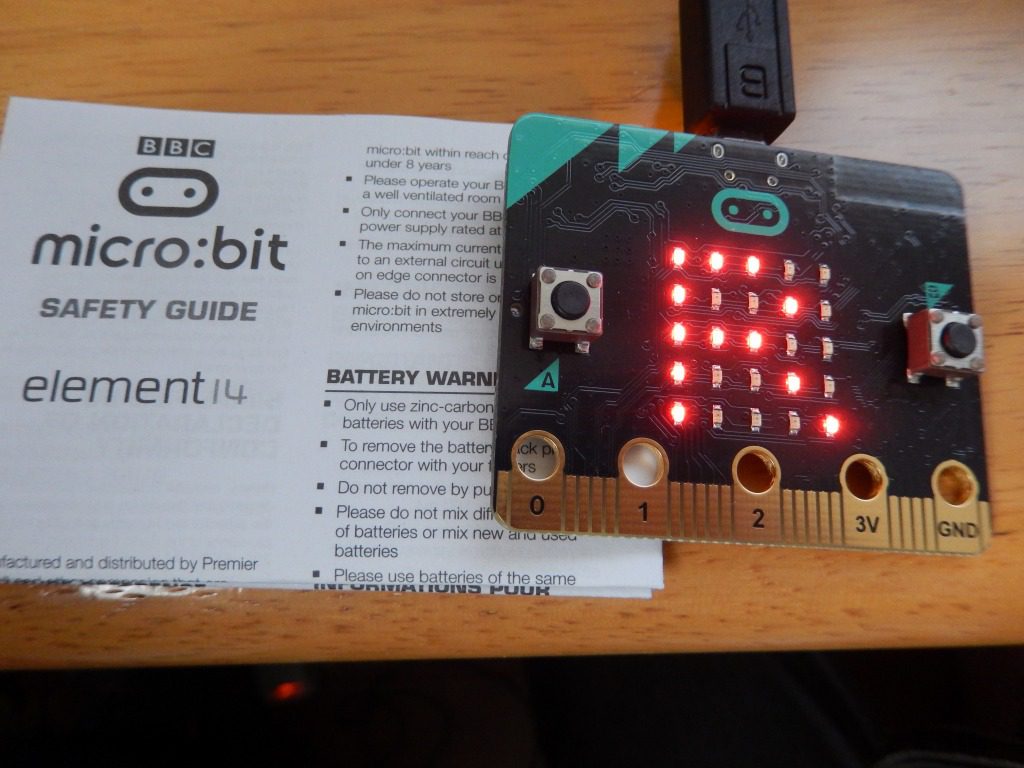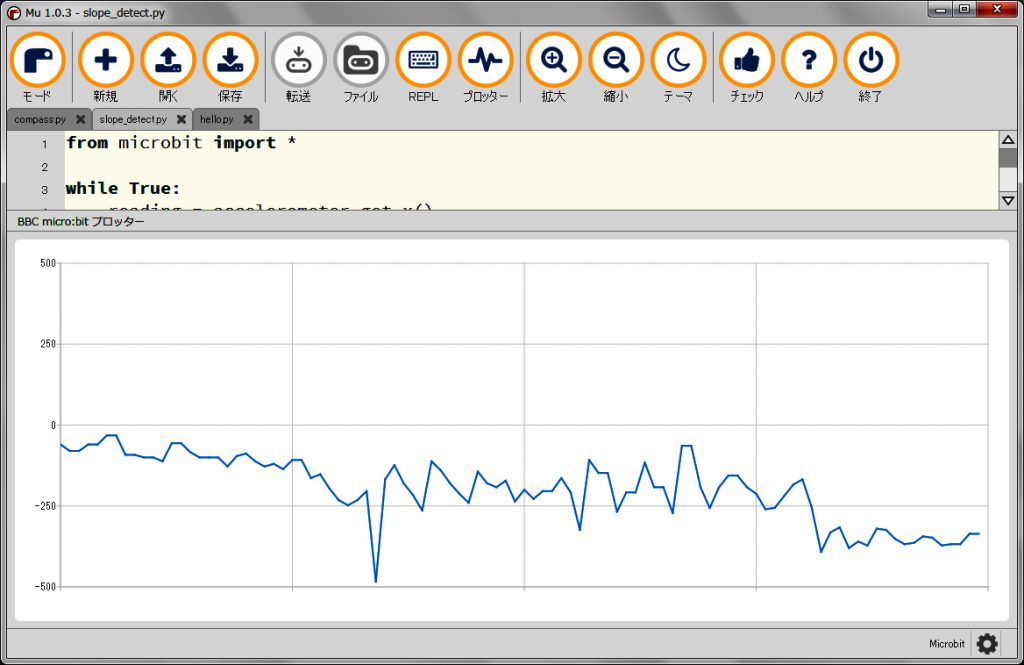さて、前問を拡張して以下のように問題を考える。
整数値が三つあり、先の二つの整数の和と第三の整数との加法、減法、乗法、除法を表現することを考える
表現1
a<-3 整数値を入れる箱を用意しaというラベルを貼る。そして3を入れる
b<-2 整数値を入れる箱を用意しbというラベルを貼る。そして2を入れる
c<-5
(a+b)+c?
(a+b)-c?
(a+b)Xc?
cが0ならば
cが0です!
そうでなければ
(a+b)÷c?
括弧は演算の優先順序が高いことを示す。
表現2
a<-3 整数値を入れる箱を用意しaというラベルを貼る。そして3を入れる
b<-2 整数値を入れる箱を用意しbというラベルを貼る。そして2を入れる
c<-5
t<-a+b 整数を入れる箱を用意しtというラベルを貼る。a+bの結果をしまう。
t+c?
t-c?
tXc?
cが0ならば
cが0です!
そうでなければ
t÷c?
このようにすると無駄な計算をしないで表現できる。