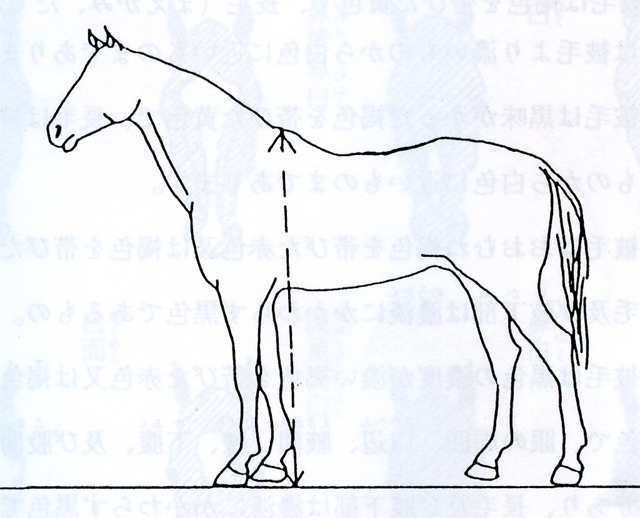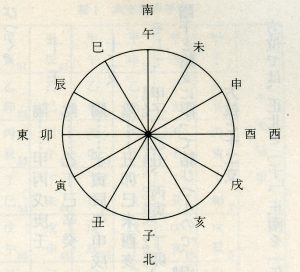日本の星の呼び方に馬起源のものがあるか調べてみている。「クラカケ星」については以前に触れた。今日は、「ウマノツラ星」について述べる。これは牡牛座のα(アルファ)星であるアルデバランとヒヤデス星団の四星を結んで出来る細長い三角形である。画像では画面左中央にアルデバランが明るく見える。日本の多くの地方でこの星のつながりを「ツリガネ星」(釣り鐘星)と呼んでいる。これを「ウマノツラ星」と呼んでいる地方がある。山形地方である(野尻抱影著「日本の星」)。
—

ウマノツラ星
—
沖縄ではこれを「ンマノチラブシ」(馬の面星)と呼ぶ地域がある(内田武志著「星の方言と民俗」)。また、茨城県では「オモツラボシ」と呼ぶ地域がある。いずれも、星を結んで出来る細長い三角形に因んで付けられた星の名前である。
ところで、東北地方では雪よけにかぶる細長い頭巾(多分わらで出来た)も「ウマノツラ」と呼ぶらしい。これもその形が馬の頭に似ているからにちがいないが、まだ実物を見たことがない。