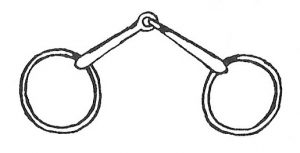馬体の名称の英語名と日本語名をとの対応表である。
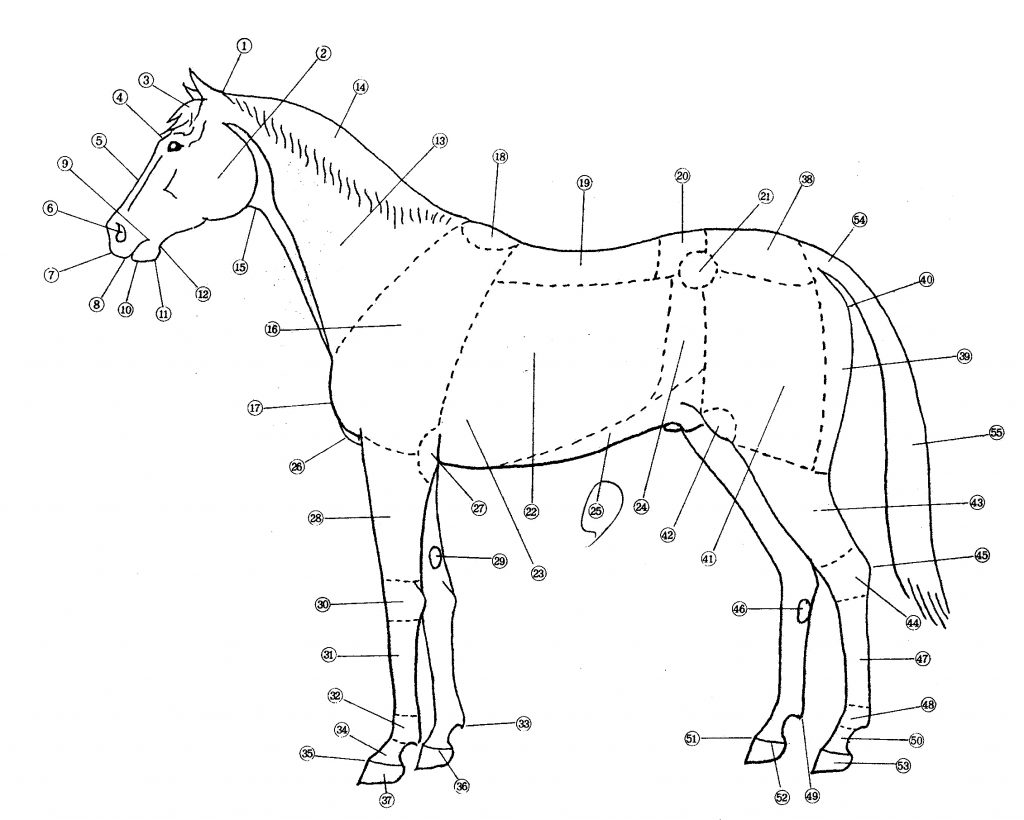
(A)頭部
- 項(うなじ)-> Nape of the neck(Pole)
- 頬(ほほ)-> Cheek
- まえがみ-> Forelock
- 額(ひたい)-> Forehead
- 鼻梁(びりょう)-> Face
- 鼻孔(びこう)-> Nostril
- 鼻端(びたん)-> Nose tip
- 上唇(じょうしん)-> Upper lip
- 口角(くちかど)-> place for the curb-chain
- 下唇(かしん)-> Under lip
- 頤(おとがい)-> Chin
- 頤凹(おとがいくぼ)