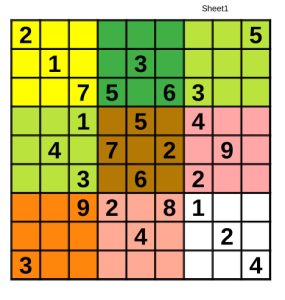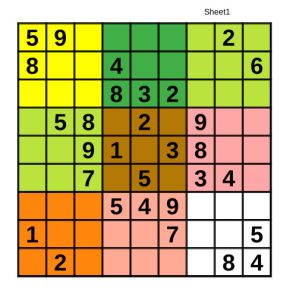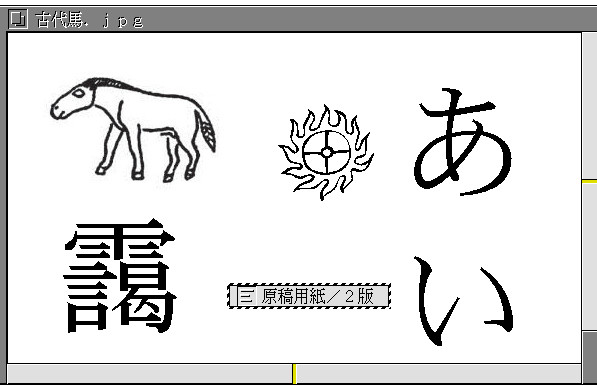“The Big Book Of Cats”の中にあったウマとネコの挿話
There’s a cat in love with my horse Harpo these days. The cat is a big old barn tom, but Harpo’s a Thoroughbred, and was pretty high-strung until the cat came around. In the morning when I go to feed him that cat is always lying in the feed bin. If Harpo lies down for a nap, the cat lies down between his front legs, and Harpo is very careful not to move them. They play hide-and-seek out in the field: Harpo nickers and lowers his nose to the grass and the cat meows and pounces. Thing is, this cat doesn’t give a hoot about any other animals- not the dog or the other cats, or even the other horses. Harpo is it. And if I go for a ride, I can lift the cat up with me and he’ll stay on the way while I hold the cat and the cat holds Harpo, holding onto the mane with his teeth.
ANNE FORELLI, RESEARCH BIOLOGIST
このごろ私の馬Harpoと仲が良い一匹の猫いる。その猫は納屋暮らしの大きなオス猫、しかしHarpoはサブレッドでかなり気性が荒い。それもこの猫が出現するまでは。朝に馬に餌をやろうとして厩にいってみると、その猫はいつも餌箱に横たわっていた。Harpoが眠りのために横になると、この猫は馬の前足の間に横になる。Harpoはこの猫のじゃまにならないよう慎重だ。
馬場ではふたりはかくれんぼをする。Harpoは嘶き草に鼻を押し付ける、その猫はみゃあと鳴き突然に現れる。この猫は他の動物、イヌ、ネコ、そしてウマには無関心である。Harpoだからである。
私がHarpoに乗るときは、その猫を私の前に引き上げと、猫はそのまま乗り続ける。それで私が猫を抱き、猫はタテガミを歯で掴んでHarpoを抱くことになる。