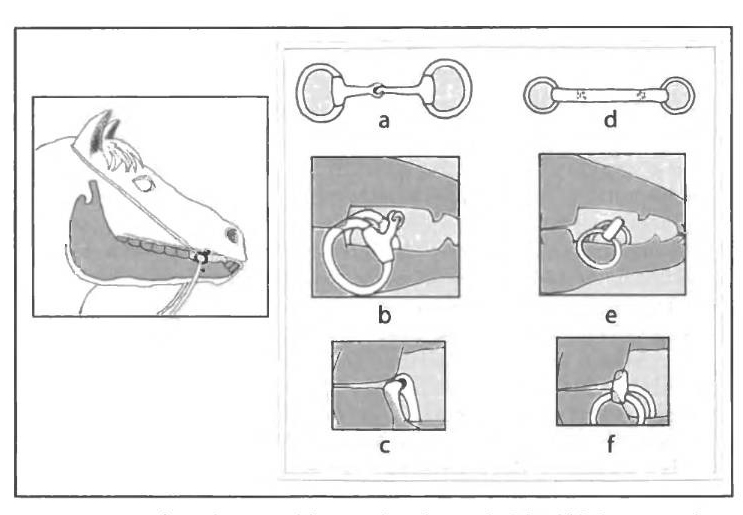ウマの家畜化の過程の問題である。
現生ウマの遺伝的な特性を調べてみると興味ある事実が出てくる。
現生ウマ全てが家畜ウマであるが、現生家畜馬の「雌」の系統は極端に分散している。母から娘に変化なして伝わるミトコンドリアDNAから得られた遺伝形質は地球上いる現生ウマの雌のこの部分の分散を説明するためには十七の系統発生的な系列に分類される六十七頭の祖先牝ウマを必要とすることが分っている。野生の牝ウマは多くの異なった場所と時間で家畜ウマに取り込まれたにちがいない。
一方雄から雄子ウマに変化なしで伝わるY染色体に関わる現生「雄」ウマのDNAは極めて一様であることが分っている。たった一頭の野生雄ウマの家畜化があったくらいで説明が着く。
野生ウマを捕獲した人々はいろんな野生牝ウマを捕獲し飼育するとに関し気楽に行っていたが、このデータに従えばかれらは野生の雄ウマをどこでも拒否し、家畜化された牝ウマたちと掛け合わせた野生の雄ウマから生まれた雄子ウマさえも家畜化しなかったことになる。現生ウマたちは極少数の原始雄ウマと多くの変化に富んだ原始牝ウマの後裔である。