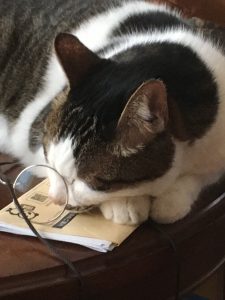最近ではプリンタもネットワーク上にあるものを使っている。複合機であればスキャナーもネットワーク上にある。そのようなスキャナーを使うときにはスキャナーに原稿をセットしてPCのスキャナー操作プログラムを実行することになる。よくあるケースではセットした原稿が厚くてスキャナーカバーを手で押さえておかなければならない。さてどうする?
筆者の使っているEpsonの複合機ではこのような状況をスマートに解決する仕掛けを持っている。それがEpsonEventManagerである。
- 複合機のスキャナーにはスキャンしたデータを保存(転送)する仕方を選択できる。「本体のメモリーカード」「スキャンしてパソコンへ」等。この「スキャンしてパソコンへ」を選択しスキャンをするとスキャンデータは自動的にPCへ転送される。スキャンの操作がスキャナーのところで全てできる。
- そのためにはEpsonEventManagerをPCのバックグランドで走らせておく。スキャナーの信号はこのプログラムで検出・処理される。
- このデーモンの動作を指示(スキャナーのデータを保存する場所等)するGUIがある。これがEpsonEventManager(ややこしい)で一般ユーザでも使えるが、複数人がスキャナーを使う場合はいちいち設定する必要があるらしく不便。管理者で全てのユーザがアクセス可能なパブリック領域の結果の保存場所に設定しておくと一度だけの設定で便利。
これで所期の目的は達成。
しかしスキャナーを使う機会はそう多くはない。デーモンはさしあたり停止しておく。